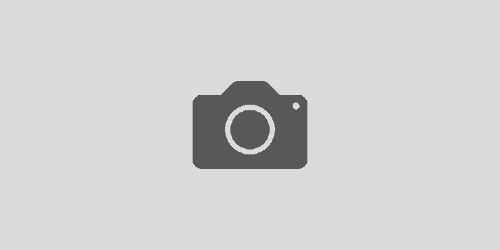「脳卒中」の症状が多彩な理由
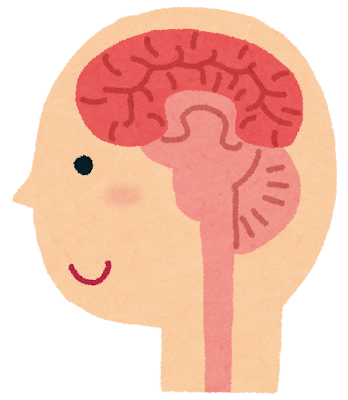
こんにちは
今回は病気の話です。
よく耳にする「脳卒中」は一般的な名称で、医学用語では「脳血管障害」と呼ばれます。
脳血管障害にはいくつかのタイプがあり、起こる症状も多彩です。
脳卒中(脳血管障害)の分類
大きく3つに分類されます。
脳梗塞(のうこうそく): 脳の血管が詰まったり、血流が悪くなる
脳出血: 脳の内部で出血する
くも膜下出血: 脳の表面の膜(軟膜、くも膜、硬膜の3層構造)のうち、軟膜とくも膜の間に出血する
そのうち、脳梗塞はさらに3つに分けられます。
心原性脳塞栓症(しんげんせいのうそくせんしょう): 心臓の中にできた血栓(血のかたまり)がはがれて、脳まで流れてきて血管が詰まる
アテローム血栓性梗塞: 脳内や首の太い動脈が詰まる
ラクナ梗塞: 細い動脈が詰まる
症状が多彩な理由
脳は部位ごとに働きが分かれています。
例えば、
大脳は、思考や記憶、理性をつかさどっています。
小脳は、身体のバランスをとる平衡機能や、姿勢を保つ機能の調整や、筋肉運動を調整します。
間脳とよばれる脳の中心に近い部分は、自律神経や内分泌機能を調整します。
脳幹は脳と脊髄の間に位置し、生命維持に欠かせない呼吸・循環・消化などの働きをつかさどっています。
脳卒中(脳血管障害)を起こして、脳のどこかの血管が詰まったり破れたりすると、脳の部位の違いにより、さまざまな症状が起こるのです。
また、大脳の中でも部位により働きが異なります。
視覚、聴覚、嗅覚、味覚、体性感覚、運動、言語などをそれぞれ担当する部位が決まっています。
このように、脳の働きは部位により決まっており、どの部分の脳血管がつまる・出血するかによって、あらわれる症状は多彩になるのです。
他の方と同じ症状とは限らない
例えば、同じ「心原性脳塞栓症」になったとしても、詰まる血管が違うと、あらわれる症状は違います。
病名は同じでも、症状の種類や程度が違うわけです。
そこが脳卒中(脳血管障害)の症状の分かりにくさかもしれません。
よく見られる症状については、次の機会にご紹介します。
投稿者プロフィール

-
作業療法士をしています。
読書と山歩き、音楽が好きです。
詳しいプロフィールはこちら。
最新の投稿
- 2024年4月28日山歩き六甲山へ登る 仮設トイレが設置されています 有馬温泉→六甲最高峰→有馬温泉【2023年4月28日】
- 2024年4月15日いろいろ新型コロナウイルス感染症 11~17日目
- 2024年4月8日リハビリ・医療新型コロナウイルス感染症 9~10日目
- 2024年4月6日リハビリ・医療新型コロナウイルス感染症 7~8日目