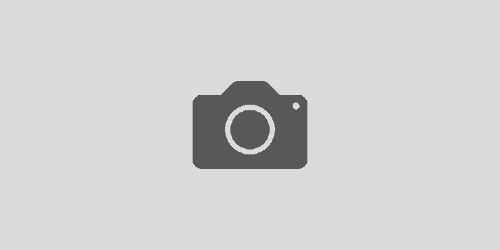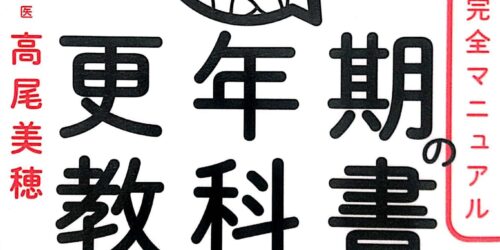【本】認知症になった専門医が語る大切なこと 「ボクはやっと認知症のことがわかった」長谷川和夫氏
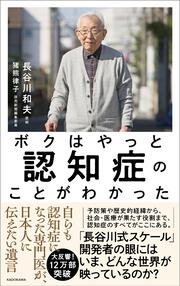
こんにちは
本の紹介です。
著者の長谷川和夫先生は、認知症界ではレジェンド、知らない方はいないと思います。
認知症のスクリーニング検査である「長谷川式簡易知能評価スケール」を他の先生方と1974年(!)に発表されています。
その長谷川先生は2017年、88歳の時に認知症であることを公表されました。
本書では認知症について、専門医として、当事者として、大切なことを多く語っておられます。
ボクはやっと認知症のことがわかった
長谷川和夫 猪熊律子 著 KADOKAWA 2019年
KADOKAWAのHPより引用
『NHKスペシャル』著者出演で大反響 感動の声が広がっています
目次
第1章 認知症になったボク
第2章 認知症とは何か
第3章 認知症になってわかったこと
第4章 「長谷川式スケール」開発秘話
第5章 認知症の歴史
第6章 社会は、医療は何ができるか
第7章 日本人に伝えたい遺言
認知症の当事者として、大切なことを多く書かれています。特に心に残ったことをご紹介します。
認知症の本質は「暮らしの障害」
それまで当たり前にできていたことがうまく行えなくなる。
暮らしは、周囲の人との関わりによって大いに変わってくるもの。周囲が、認知症の人をそのままの状態で受け入れてくれることが最も重要。
その人との接し方を、それまでと同じようにすること、自分と同じ「人」であるということを第一に考えることが大切です。
私たちは「認知症の方」と思って、そのままの状態ではなく、こちらが勝手に、分かりやすいようにと、必要以上に「それまでと少し違った形で」接しているのかもしれません・・
自分の体験の「確かさ」が揺らぐ
自分のやったことと、やらなかったことに対して確信が持てない。
家の鍵をかけたかどうか不安になっても、確かに鍵をかけたと思えばそのまま出かけるけれど、確かさが揺らいでくると、家に戻って確認しても、それがまたあやふやになって、いつまでたっても確信が持てない。
「確かさ」が揺らぐ・・ その不安はどれほどでしょうか。何度確認しても確信が持てない・・
認知症の方はそのような中に生きていることを、知っておくことが大切だと思います。
連続して生きている 認知症は「固定されたものではない」
人間は生まれた時からずっと連続して生きているので、認知症になったからといって、人が急に変わるわけではない。昨日まで生きてきた続きの自分がそこにいる。
認知症は、普通の時との連続性がある。長谷川先生の場合は、朝起きた時が一番調子がよく、午後遅くなると、自分がどこにいるのか、何をしているのか分からなくなってくる。
「認知症はなったらもうそれは変わらない、普遍的なものだと思っていた。これほどよくなったり、悪くなったりとグラデーションがあるとは、考えてもみなかった」と話されています。
関わる方が、「認知症の方」とひとくくりにしている面があると思います。1人1人はみんな違う人、しっかりとその方を見て、話を聴くことが大切なのでしょう。
認知症を理解する
認知症についての正しい知識を皆さんに持っていただきたい。
何もわからないと決めつけて置き去りにしないで。本人抜きに物事を決めないで。時間がかかることを理解して、暮らしの支えになってほしい。
認知症の人の言葉をよく聴いてほしい。聴くということは待つということ。待つということは、その人に時間を差し上げること。
「その人に時間を差し上げる」という視点がありませんでした。聴くのに時間がかかるな・・ と思ったことは何度もあります。理解すると頭では分かっているつもりでも、行動がそうなっていなければ意味がないですね。
2020年1月には、NHKスペシャル「認知症の第一人者が認知症になった」が放送されました。
番組を基に「NスぺPlus」でも記事が掲載されています。
認知症は多くの方に関係のある話題になっています。興味のある方は、ご一読されてはいかがでしょうか。
投稿者プロフィール

-
作業療法士をしています。
読書と山歩き、音楽が好きです。
詳しいプロフィールはこちら。
最新の投稿
- 2024年4月28日山歩き六甲山へ登る 仮設トイレが設置されています 有馬温泉→六甲最高峰→有馬温泉【2023年4月28日】
- 2024年4月15日いろいろ新型コロナウイルス感染症 11~17日目
- 2024年4月8日リハビリ・医療新型コロナウイルス感染症 9~10日目
- 2024年4月6日リハビリ・医療新型コロナウイルス感染症 7~8日目